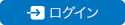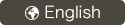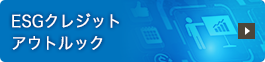お知らせ
- ハイブリッド証券の資本性の評価について
- 2006.09.01
- 株式会社日本格付研究所(JCR)は、このたび、優先株を含むハイブリッド証券の資本性の評価に関し、以下のとおり、基本的な視点・目安を整理しました。
JCRでは、ハイブリッド証券の格付けについての考え方も、同時にとりまとめました。これについては本件と同時発表のプレスリリース06-D-416をご覧ください。
1.資本性の評価における検討項目
ハイブリッド証券には、劣後債、優先証券、優先出資証券、優先株など、様々な証券が含まれる。満期が定められている場合があったり、利息・配当の率のステップアップがあったりする点で、普通株と異なるものの、一定の事由を満たす場合に利息・配当、場合によっては元本をデフォルト(債務不履行、契約に違背するかたちでの不払い)することなく繰り延べられる繰延条項や、発行体破綻時の請求権順位で一般債権より劣後する劣後条項などを付することで、キャッシュアウトの柔軟性と破綻時の請求権順位の点で普通株に似た性質を一部備えた証券である。
債権者からみた場合、普通株は主に、(A)ストレス時などのキャッシュアウトを抑制することで財務内容に柔軟性・安定性をもたらし、発行体がデフォルトに至る可能性を減らす、(B)ストレス時に損失を吸収するバッファーとなることで、債務(債権者からみれば債権)の回収可能性を高める、という2つの機能を通じて債務履行の確実性を高める役割を果たす。普通株がもつこれら2つの機能のうち、ストレス時などのキャッシュアウトを抑制する機能は、(i)元本の償還義務・満期がない、および(ii)利息・配当支払義務がない、という普通株の特徴から主に由来するものである。そして、ストレス時に損失を吸収するバッファーとなる機能は、(iii)破綻時における請求権順位が最劣後に設定されている、という特徴から来るものである。
このため、JCRでハイブリッド証券の資本性を評価する場合、それは債権者にとって好ましい上述(A)、(B)の機能をどれだけ有するかを評価するものであり、そのために上述(i)~(iii)の特徴を当該証券がどれだけ備えているか、下表に示す契約条項などを検討し普通株との類似性を測定するアプローチを基本としている。
[普通株の特徴] [期待される効果] [関連する契約条項など]
1 元本の償還義務・満期がない ○返済圧力やリファイナンス・リスクがなく、財務の安定性・柔軟性が高まる。 ○償還期限
○コール条項
○金利・配当ステップアップ条項
○リプレイスメント・ランゲージ
○普通株転換条項
○減資の規定
2 利息・配当支払義務がなく繰り延べられた利息・配当が累積しない ○ストレス時にキャッシュアウトを抑制でき、財務の安定性・柔軟性が高まる。
○繰り延べがデフォルト、クロスデフォルトに抵触しない。 ○利息・配当の繰延条項(強制・任意)
○累積・非累積
○強制支払条項
○デフォルト事由
3 破綻時における請求権順位が最劣後である ○破綻時の回収可能性が高まる。 ○残余財産分配条項
○劣後特約
以下において、上述(i)~(iii)の特徴それぞれについて普通株との類似性を評価し、資本性の判断に結びつけるうえでの考え方、留意点を示す。
2.証券の属性・商品設計にもとづく資本性の評価
(1)元本の償還義務・満期のない点
通常の債務は一定の期間のなかでの元本の分割返済または一括返済が義務となっており、その義務の不履行(デフォルト)は他債務のクロス・デフォルト条項などを通じて発行体の破綻につながることになる。普通株には償還義務と満期がないため、財務の柔軟性・安定性が高まり、償還に伴うデフォルトあるいは財務内容・資金繰りの悪化の可能性を低下させることになる。
A.期間
普通株のもつ満期の面でのメリットを証券に備えるには、期間が永久であることが最も望ましいのは言うまでもないが、税制上の観点などから満期を設けるハイブリッド証券が少なくない。満期の規定は資本性の評価にはマイナスとなる。もっとも、期間が超長期の場合には、通常の債務よりも普通株との類似性が認められる余地が出てくる。
B.コール、金利・配当ステップアップ
永久あるいは超長期であっても、コール(発行体の任意による期限前償還)条項が付いたハイブリッド証券は多い。コール条項付証券は、発行体にとってはより有利な条件での借り換えなどの選択肢を広げられるメリットをもち、他方、投資家にとっては高めのリスクに見合ったリターンを得つつも比較的早期の元本回収の可能性を期待できる点で魅力的である。
発行体が実際にコールに踏み切る蓋然性が高ければ、当該証券の満期は実質的にはコール行使期限と同じとみなされよう。特にコール行使期限以降に金利・配当が自動的に引き上げられるステップアップ条項(アップ幅は100bp程度が一般的)が付いている場合や当初調達コストの水準が非常に高い場合は、発行体が調達コストの抑制のためコールに踏み切る蓋然性が高いと判断され、満期の観点からみた普通株との類似性は低いとみることになる。
もっとも、ステップアップ条項を伴わず、当初調達コストも低い場合は、コールの蓋然性は、発行体の財務状況および運営方針、投資家のコールに対する期待の度合いなどにより様々と言える。この場合、満期の観点からみた普通株との類似性はコール条項がない場合より低いと判断されるが、その程度の評価は一律ではなく個別の事情を勘案する部分が大きくなろう。
C.リプレイスメント・ランゲージ
コールの蓋然性が高いと考えられる証券であっても、資本性が当該証券と同等あるいはより高い証券をコール以前に発行して代わり金を当該証券の償還にあてる旨意思表明する文言、いわゆるリプレイスメント・ランゲージがあり、その実行の可能性が高いと認められる場合には、実質的な満期が相応に長く、普通株との類似性は補強されると考えることができる。
リプレイスメント・ランゲージは、海外では、契約のかたちをとりその対象となるシニア債務等の債権者が発行体に履行を強制する権利を与えるものが一部みられるものの、多くは契約ではなく目論見書などでの意思表明のかたちをとる。目論見書では、債権者等は発行体に意思表明の内容の履行を強制する権利をもたない。とはいえ、株式を上場していたり債券を公募発行していたりして、資本市場からの信認が重要な意味を有する発行体の場合には目論見書での意思表明も相応に重い意味をもつと考えられる。このような発行体のリプレイスメント・ランゲージについてはコール条項によるマイナスを緩和するものとみることができよう。
D.普通株への転換条項
証券が普通株に転換されれば当該証券の満期はなくなるため、転換の可能性が極めて高い場合は普通株との類似性は高いと考えられる。
普通株への転換の可能性を判断するうえでは、転換が任意か強制か、株価と比べた転換価格の水準、転換までの期間などが重要になろう。投資家の意欲と無関係に普通株に転換される強制転換型証券の場合は、強制転換までの期間が3年以内と短ければ、転換の可能性は任意転換型証券より高いと言える。転換社債のように普通株への転換が任意の場合は、株価水準に比べ転換価格が相当低ければ転換の可能性はある程度見込まれるものの、株価が変動すること、および転換があくまで投資家の意思に左右されるものであることから、転換の可能性が極めて高いとは基本的には判断しにくい。
E.減資の対象
経営不振の企業が新たな外部資本を導入する際、配当を可能にするなどの目的で過去の累積損失を調達資金との相殺により解消することが多い。この際用いられるのは、負債の債権放棄やDES(債務と株式の交換)と、普通株や優先株の減資である。前者の場合は当該証券のデフォルト(契約に違背するかたちでの不払い)に該当し、後者の場合はデフォルトに該当しない。このように、法的に償還義務がない証券は、キャッシュアウトの抑制に役立つだけでなく、デフォルトを生じさせることなく過去から累積した損失を吸収・解消し財務再編に寄与することができる点で、償還義務のある証券より財務の柔軟性に寄与すると言える。
もっとも、わが国での事例をみると、減資の対象であることのメリットが発揮されるのは、発行体の財務内容が相当悪化した後であることが多く、また、減資となっても負債の債権放棄やDESを伴ったものが少なくない。言い換えれば、減資が一部の負債の回収可能性を高めはしたものの発行体のデフォルトの可能性を低下させたとは言いがたいケースが少なくない。したがって、減資の対象という特徴は、財務面での柔軟性によりデフォルトの可能性を低下させられるかどうかという観点での資本性の評価のなかでは、基本的に二次的な位置づけとなる。
(2)利息・配当の支払義務のない点
普通株の場合、会社法により配当を含む剰余金の分配に財源規制がかけられ、分配財源が枯渇した場合には配当が強制的に停止あるいは減額されるが、たとえ分配財源が枯渇していなくとも配当の停止・減額が発行体の任意で可能であり、また、配当の不払いは法律上デフォルト(契約に違背するかたちでの不払い)とならない。このように普通株は配当支払いに関し、(i)ストレスが比較的小さい段階でもキャッシュアウトを任意に抑制できるという意味での財務上のデフォルト回避機能(財務上の柔軟性)、(ii)不払いがデフォルトを構成しないという法律上のデフォルト回避機能を有する。
A.任意繰り延べと強制繰り延べ
ハイブリッド証券の多くは利息・配当繰延条項を伴っており、繰延条項が定める一定の条件(繰延事由)に抵触した場合の利息・配当の繰り延べ(不払い含む)はデフォルトに該当しない仕組みとなっている。法律上のデフォルト回避機能は多くの証券の場合が備えていると言える。
しかし、ハイブリッド証券の場合、利息・配当の継続的・安定的な支払いに期待する投資家が多い。発行体は、定期の安定収入を期待する投資家に購入された証券の利息・配当の繰り延べが投資家の信認を傷付け、それが後の資金調達に不利に働くことを懸念し、かなりのストレス状況にならない限り利息・配当の支払いを継続しようとするだろう。繰延条項があるからといって、財務上の柔軟性(デフォルト回避機能)が常に認められるわけではない。特に繰延事由に抵触しても繰り延べが発行体の任意に委ねられる任意繰延条項しか付いていない証券の場合、普通株の分配財源が枯渇し普通株配当が停止する段階になっても、発行体が利息・配当支払いを継続する可能性がある。このため利息・配当に関しては、ストレス時には繰り延べられる裁量がある点では普通株との類似性が認められるものの、その類似性の程度は高くないと判断することになる。繰り延べにより優先株に議決権が生じるなど、繰り延べが発行体の嫌う状況を招く仕組みとなっている場合には、その評価はさらに低くなる。
他方、繰延事由抵触時に強制的に繰り延べが行われる強制繰延条項が付いている場合には、任意繰延条項のみの場合のような懸念はなく、利息・配当に関しては普通株との類似性は高いと判断することになる。
B.繰延事由
もっとも、繰延条項をポジティブに評価するには、繰延事由が適切な水準で設定されていることが前提で、発行体の債務がデフォルトになるよりも相応に早期の段階、具体的には少なくとも普通株の分配財源枯渇の段階ではキャッシュアウトの抑制が行われるよう、トリガーが設定されることが必要である。
C.累積・非累積
繰り延べられた利息・配当が累積し、繰延事由に該当しなくなった場合などに支払われるとする累積条項は、特に繰り延べが発行体の任意で行われかつ累積される場合、将来支払う必要のあるものを繰り延べる発行体のインセンティブは低くなるので資本性の評価を低める要素となる。
D.強制支払条項
過去にある事由が生じた場合には利息・配当支払いが強制的に行われるよう定めるのが強制支払条項である。よくみられるものとしては、ある年度(例として07/3期)にかかる普通株の配当が行われれば、その次の年度(08/3期)のハイブリッド証券の配当(たとえば毎年度9月、3月)は繰延事由への抵触があろうとも支払われなければならないとされている証券がある。普通株の中間配当も普通株の期末配当の前払いとして含まれるケースであれば、普通株中間配当がたとえば06年7月に行われた場合には、08/3期のハイブリッド証券配当は08年3月分も含め支払われることになる。逆に言えば、この例では08年3月のハイブリッド証券配当を止めるには、20ヶ月前の06年7月の普通株中間配当をあらかじめ止めておく必要がある。この例のように1年以上過去の事由が利息・配当の繰り延べを強制繰延条項に基づくものも含めて制約する場合には、利息・配当に関する普通株との類似性は低いものとみられる。
(3)破綻時の請求権順位が最劣後である点
普通株は破綻時における請求権順位が最劣後であり、破綻時の「債務の回収可能性」を高める機能(劣後性)を有する。このため、ハイブリッド証券の破綻時の請求権を評価するに際には、債務全般と比した順位が重要となる。言い換えれば、優先株などと比べ順位が上か下かは大きな問題とならないが、より下位の債務が存在するあるいは存在しうるのであれば、劣後性の面で普通株との類似性がやや弱いとみなすことになる。
もっとも、劣後性の評価は、元本の償還義務・満期がない点、および利息・配当支払義務がない点に比べ、ハイブリッド証券の資本性評価における位置づけは二次的となる。資本性の評価は発行体の債務履行の確実性の分析に役立てることを目的に行うものであるが、債務履行の確実性は、発行体が破綻することなく事業を続け必要なキャッシュフローを継続的に得ていけるかどうかに多くを負うと考えられる。破綻後の回収可能性の評価を債務履行能力の分析の中心に据えることは適当ではなく、同様に、資本性の評価においても回収可能性に関連する項目の分析に大きな比重を置くことは、発行体の信用力がかなり低い場合を除いては適当ではない。
(4)その他
当該証券がバランスシート上負債の部に入るか、資本・純資産の部に入るかといった、会計上の分類については、それ自体を資本性の評価に織り込むことは原則としてしない。負債の場合は通常、繰延事由に抵触しない限り元利支払義務があるので、資本・純資産の部に入る資金調達手段に比べ、デフォルトのリスクが存在し財務上の柔軟性も劣る。また、普通株・優先株は負債と異なり買入消却をするにはそれに相当する分配財源がなければならないことから、買い入れされる可能性は負債に分類される証券がコールされる可能性より低いと思われる。また、負債であれば、資本に分類される証券よりも投資家の利息・配当への期待が強く、発行体が繰り延べを回避する可能性が資本の場合よりも高いかもしれない。しかしこれらの要素は、上記の各項目につき資本との類似性を検討するなかで、個別に評価に織り込んでいくことになる。
(5)証券属性の分類
ハイブリッド証券の属性(商品設計)について、検討すべき主要な項目として3つをあげ、その評価ポイントを述べてきた。証券の属性の評価にあたってはこれらの項目の評価を総合し、その資本性を以下のように4つのレベルに分類する。
[資本性] [分析時の目安] [該 当 例]
債務同等 0 ・期限付き、利息・配当繰延不可の劣後債
低 25 ・超長期/永久、コール可能、金利・配当ステップアップ、利息・配当繰延可能(任意繰延条項のみ)の劣後債/優先証券/優先株
中 50 ・超長期/永久、コール可能、金利・配当ステップアップ、リプレイスメント表明あり、利息・配当繰延可能の劣後債/優先証券/優先株
高 75 ・超長期/永久、コール不可、配当繰延可能(強制繰延・非累積)の優先証券/優先株
・3年以内の強制転換条項付の優先株(非累積)
普通株 100
3.発行体の個別事情も加味した総合評価
以上、証券属性(商品設計)のみにもとづいて評価を行う際の考え方を述べてきたが、証券のコールや利息・配当の繰り延べなどは発行体の個別事情に左右される部分が大きい。このため発行体の個別事情を加味して、証券属性(商品設計)のみにもとづく普通株との類似性の評価を補正したうえで、最終的に資本性の判断を行う。
個別事情としては、発行体の財務運営方針が重要である。たとえば発行体経営陣がハイブリッド証券をコールすると資金繰り、株価、格付けなどに悪影響が出ると考えていると判断される場合などには、コールの蓋然性は、比較的小さいと判断できるケースがあるであろう。ただし、発行体の表明する財務運営方針だけをもって、コールの蓋然性が小さいと判断することは難しい。発行体の財務運営方針が合理的な基礎を有しているか、財務内容を検討し、慎重に判断することとなろう。
財務内容の検討には、ハイブリッド証券が発行体の財務に占める位置づけも含まれる。ハイブリッド証券が資金調達に占める比重が大きい場合、発行体は利息・配当繰り延べが投資家の信認を傷つけ後の資金調達に支障をきたすことを懸念し、繰り延べを嫌う傾向を強めるかもしれない。
普通株への転換条項付の証券を評価する場合には、転換に伴う株式の希薄化や株主構成の変化を嫌い、発行体がコールする可能性があるため、普通株転換に対する発行体の許容度の検討が必要である。強制転換型で転換までの期間が3年以内と短い証券であっても、満期にかかる資本性の評価が高いと最終的に判断するには、大幅な株式希薄化や発行体の嫌う株主構成の変化といった懸念がなく、発行体が普通株転換を明らかに許容し転換を前提として財務運営等を行っていることが確認されなければならない。
発行体の財務運営方針を判断するうえでは、証券の保有者の性格や保有目的も重要である。公募発行を通じ購入した一般の機関投資家であれば、ハイブリッド証券の利息・配当について定期の安定収入を期待している場合が少なくないと考えられ、繰り延べの余地が比較的小さくなってくると考えられる。他方で、保有者が発行体の親会社や発行体との戦略的提携を意図する企業で、転売等の意図が認められないような場合は、利息・配当を繰り延べたりコール行使期限でも償還しないことが許容される余地が拡大する。
これまで述べてきた考え方はすべての業種のハイブリッド証券の資本性の評価の基礎となるものであるが、業種間で資本性の評価に若干の違いが生じることもある。具体的には、金融機関については、規制・監督当局の意向が発行体の財務運営に影響を及ぼしやすい点が評価に反映されることとなろう。たとえば銀行の場合、ハイブリッド証券のコールにあたっては通常、当局の認可が前提とされている。このため、財務上のストレスがかかりつつある状況のもとでは代替的な資金調達なしにコールされるという事態が生じる蓋然性が比較的低くなるとみられる。また、銀行のハイブリッド証券は資金調達に占める割合が他業種より高くかつ市場で広く保有されており、利息・配当の繰り延べは個別銀行の資金調達環境の悪化のほか金融システム不安にもつながりかねない。このため当局は利息・配当に関しても通常重大な関心をもち、その意向が発行体の利息・配当の支払いに関する方針にも影響を及ぼすとみられる。このような事情から、金融機関については似たような商品設計の証券であっても資本性の評価が一般事業法人とは異なる場合がある。(生命保険会社のハイブリッド資本の評価に関しては、本件と同時発表のプレスリリース06-D-417もご参照ください。)
以上のように資本性の評価にあたり検討すべき発行体の個別事情は多岐にわたる。資本性の評価の基本は発行体を縛る証券属性(商品設計)の分析にあるのは確かであるが、コールのように発行体の任意に基づき機能する証券属性がある以上、資本性の評価が個別事情により大きく左右されることにも留意が必要である。
PDF