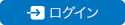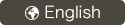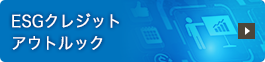お知らせ
JCR行動規範の制定について
2005.05.31
JCR行動規範の制定について
PDF